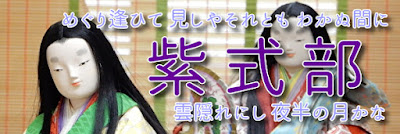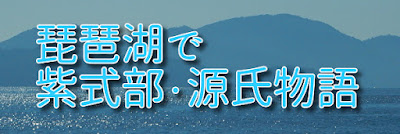大河ドラマ「光る君へ」の最終回では、
藤原道長が最期を迎える時、
紫式部は道長に「戦のない泰平の世を護られました」と語っていました。
ただ、最後の言葉は「嵐がくるわ」でした。
1027年(万寿4年)12月4日、
道長が薨去すると、翌年、東国では平忠常が反乱を起こします(平忠常の乱)。
忠常は
高望王流桓武平氏。
「光る君へ」に登場した双寿丸が仕えた
平為賢と同族。
東国で「新皇」を称して反乱を起こし、940年(天慶3年)に平貞盛と藤原秀郷らに討ち取られた
平将門の孫。
将門以来の大規模な反乱となった平忠常の乱は、摂関政治を終わらせるきっかけとなります。
これは、道長の時代に起こった
刀伊の入寇での朝廷の無策と、活躍した武者(のちの武士)たちの恩賞が不十分であった事が原因の一つと考えられています。
平忠常の乱を鎮めたのは、
経基流清和源氏の一流
河内源氏の祖
源頼信。
頼信は、
道長四天王の一人でした。
1051年(永承6年)には、陸奥国で勢力を広げていた安倍頼良と陸奥守・藤原登任の間で戦いが起こりますが、この反乱を鎮めたのは、河内源氏二代棟梁の
頼義とその子
義家(前九年の役)。
義家は、その後の後三年の役(1183-1087)でも活躍しますが、朝廷は私闘と判断して恩賞を与えなかったたため、義家は従軍した坂東武者たちに私財から恩賞を与えて「武神」と称えられています。
そして、1086年(応徳2年)、白河上皇が院政を開始し、200年以上続いた摂関政治が終わります。
ただ、院政期に特別な扱いを受けたのは、東国の反乱に活躍した
河内源氏ではなく、伊勢平氏でした。
伊勢平氏も
高望王流桓武平氏。
伊勢国を拠点とした一族ですが、地盤を築いたのは
道長四天王の一人だった平維衡。
そして、子孫の
平清盛が1159年(平治元年)の
平治の乱で
源義朝を倒したことで源氏は没落し、平氏の勢力が拡大されます。
清盛は、
後白河院政下で武士としては初めてとなる太政大臣となり、さらに我が国初の武家政権を樹立しました。
それは
源頼朝の武家政権へと繋がっていくことになります。
参考までに・・・
頼朝は、平忠常の乱を鎮圧した
源頼信から数えて七代目。
平治の乱後、頼朝は処刑される運命にありましたが、それを救ったのが清盛の継母
池禅尼でした。
池禅尼は
刀伊の入寇で活躍した
藤原隆家の子孫。
頼朝とともに鎌倉に武家政権を創った
北条時政・
政子・
義時は、
高望王流桓武平氏の平直方の子孫といわれています。
頼朝の
源氏再興の挙兵を援けた房総半島の
千葉常胤や
上総広常は、平忠常の子孫でした。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆